裏通りからかく語りき | 人となり | 人となり | となりの人の人となり
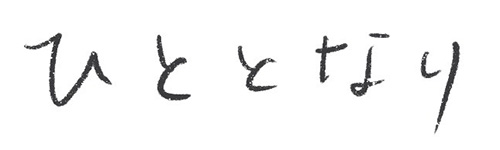
裏通りからかく語りき

6月4日はハンガリー及び周辺の国にとっては非常に重要な日である。トリアノン条約という第一次世界大戦の終結後に締結された領土分割案により敗戦国であった当時のオーストリア=ハンガリー帝国は分裂とその土地の多くを失い、今年はその調印日から100年という節目の年である。EUから独裁と指摘されている現政権を支持する者たち、反対する者たちそれぞれのデモも発生し、この年の6月4日はハンガリーにとって非常に繊細な政治的意味をもつ日であった。
ハンガリー人はお喋りが好きだ。もちろんそれはハンガリー人に限ったことではないが、彼らは夕方になると友人達とバーに集い長いこと話し込む。興味深いのはそれが週末であってもゲラゲラと騒ぐ者は稀で、多少の盛り上がりは見かけるが隣の席の会話を阻害させるような喧騒はめったに見かけない。BGMの音量も控えめで、落ち着きと静かな情熱が交差するその雰囲気は私の好きなハンガリーの情景の一つである。
目抜き通りから一本裏のとあるオープンバーである日、ラースローと名乗る男が井戸端講義を開いていた。聞くところによると彼はトランシルヴァニア出身だという。トランシルヴァニアというのはルーマニアの北西部を中心とした地方の名称であり、かの条約が調印される前までそこはハンガリーであった。現在ではルーマニア語が公用語となっているが、そこは今でもハンガリー語が通用する。ラースローという彼の名もまたハンガリー名であり、つまり彼はハンガリー系ルーマニア人である。彼は現在ブダペストのとある大学で社会学を専門とした教員として働いているという。
「僕にとってルーマニアは祖国ではあるが、幼いころから親しんできたこの言語に僕は自分のルーツを感じるんだ。果たして僕のアイデンティティはどこにあるのかな。」
その講義は彼の個人的な思いから始まった。
「僕は本当は考古学者になりたかったんだ。小さなころに見たエジプトの写真に自分の運命がそこにあるような気がしたんだ。」
不器用に巻いた煙草に火をつけ、彼は続ける。
「一生懸命お金を貯めて、なんとかハンガリーの大学に入学したんだ。本当はイギリスに行きたかったんだけど、僕の稼ぎではそれがいつになるのか検討がつかなかった。」
彼はその大学で歴史と地理学に没頭し、なかなかの成績で大学を卒業した。考古学者として独立する夢と自信に溢れていたという。
「けれど僕の夢はそこで終わったんだ。調査団への推薦は全部イギリスやアメリカ、ドイツの学生がもっていって僕の経歴は見向きもされなかった。独自に活動しようにもそんな奴にスポンサーなんてつくわけがなく、結果として僕は考古学のスタートラインにすら立てなかった。」
学生時代の教授の推薦で教員としての職は得たものの、予算のおりない考古学ではその席はなく現在の科目に落ち着いた。多少の知識はあったものの、自らの責任感ゆえラースローは社会学を一から学び直し教鞭をふるってきた。しかしその中で彼は現代における国際社会のゆがみを見たと語った。
「僕の科目は近代から現代の社会なんだけど、講義の準備をしながらものすごい憤りを感じるんだ。ベルリンの壁の崩壊はいつも注目の的になるけど、プラハの春やハンガリー動乱は大して扱われない。独裁者の話題はいつもヒトラー、スターリンだけどチャウシェスクのことはなかなか語られない。僕ら地元の人間だけが意識しているようで、国際社会でも、たとえヨーロッパでも僕たちはいつまでもマイナーな存在なんだ。」
灰皿に煙草を押しつけビールのジョッキを膝に置き、ため息をつく。
「仕方のないことなのは分かっているさ。世間に与えた影響はそれだけ大きかったんだ。」
その場の取り巻きは「わかるよ」と彼に同調し、皮肉な笑いを携えながらそれぞれの経験した例を挙げ始めた。
ラースローはビールを一口含むと同時に、何かを思い出したように一瞬眉を上げ、人差し指を軽くゆすりながらこんなことがあったと語りだした。
「学生から国連についての質問があったんだ。もちろん僕は教師として彼らの指針や活動を説明して、その理念の重要さを伝える。けれども僕は絶対に彼らを称賛はしない。」
「なぜだい?」
取り巻きの1人が残ったビールを飲み干す彼に尋ねる。ラースローは空になったジョッキを丁寧に机に戻し、続ける。
「彼らの方針は彼らの意見でしか決定されないからさ。裕福なヤツらの意見さ。経済力があるから教育が充実し、十分な仕事と生活を得て心に余裕がある人達のものの言い方さ。サスティナブルな社会の成長?立派なもんさ。そりゃあそうあるべきさ。でも僕たちに何ができる?お金がないから教育が発展できない。仕事だって大した稼ぎじゃない。安売りのスーパーで買い物するのが当たり前だけどあいつら全部ドイツ資本じゃないか!買い物をすればあいつらの稼ぎになる。それでも他に選択肢はないんだ。僕らはいつも無視されて、全ての決定は裕福なヤツらの目線でしかないんだ。僕の生まれた村では電気だってそこまで普及してないしみんな自給自足で生きている。とっくにサスティナブルな環境さ。僕らにとってはそれが当たり前なのに、先進国の目線はそこにはないんだ。」
彼らは自分たちの価値観を与えるばかりで他者から学ぼうとしない。ラースローの言葉が意味するのはおそらくそういうことなのだろう。
悔しさが滲んだ独白に、その場に少しだけ重い空気が流れた。気まずさを感じとったのかラースローは「もう一杯とってくる」といって席を立った。
「今日の講義はこれで終わりかな?あいつもこれでちょっとはスッキリできたんじゃないか?」
1人がそうつぶやくとその場にふっと優しい空気が広がった。おそらくこれまでも、彼らは毎度このバーに集まりそれぞれの気持ちを共有し合うことで互いを慰め認め合ってきたのだろう。ラースローがビールとナッツを手に席に戻ってしばらくすると話題は「昨日ナンパに失敗した相手に今朝偶然遭遇した」ことに変わっていた。
制限が緩和され始めたブダペストではレストランやバーも営業を再開し、観光客が居なくなった夜の街は地元の人々が徐々に集まるようになってきた。ここの人々にとって互いに同じ空間を共有しながらお喋りをすることは彼らのアイデンティティを確かめる大事な文化であり、そこは教養を高める学びの場なのかもしれない。今日もおそらくどこかのバーで様々な講義が行われ、人々はその時を楽しんでいる。
前の記事
ドイツ菓子の話
次の記事
ジキルとハイドの「人となり」







